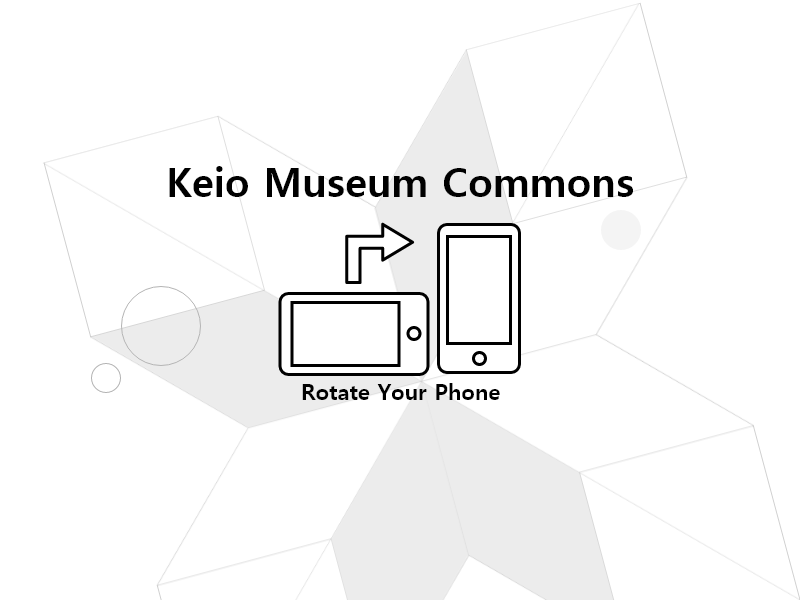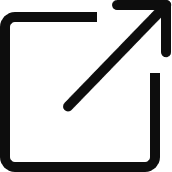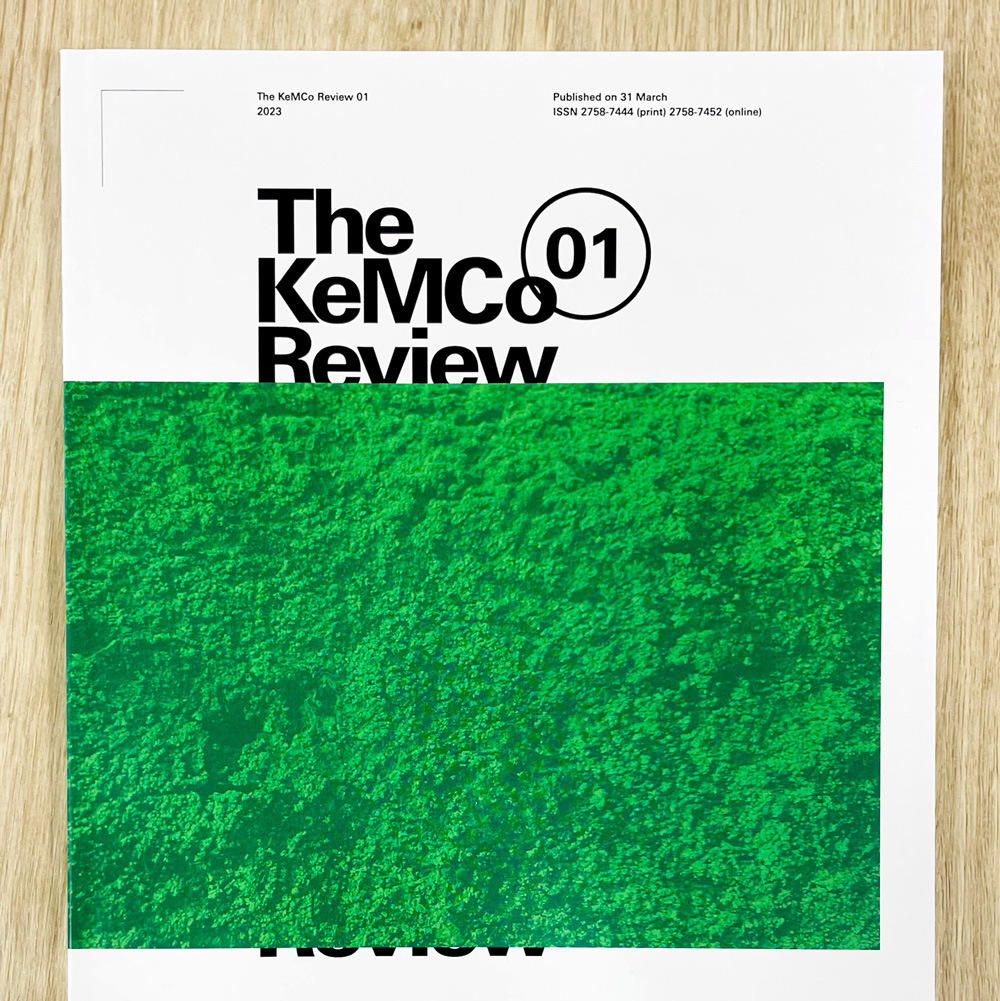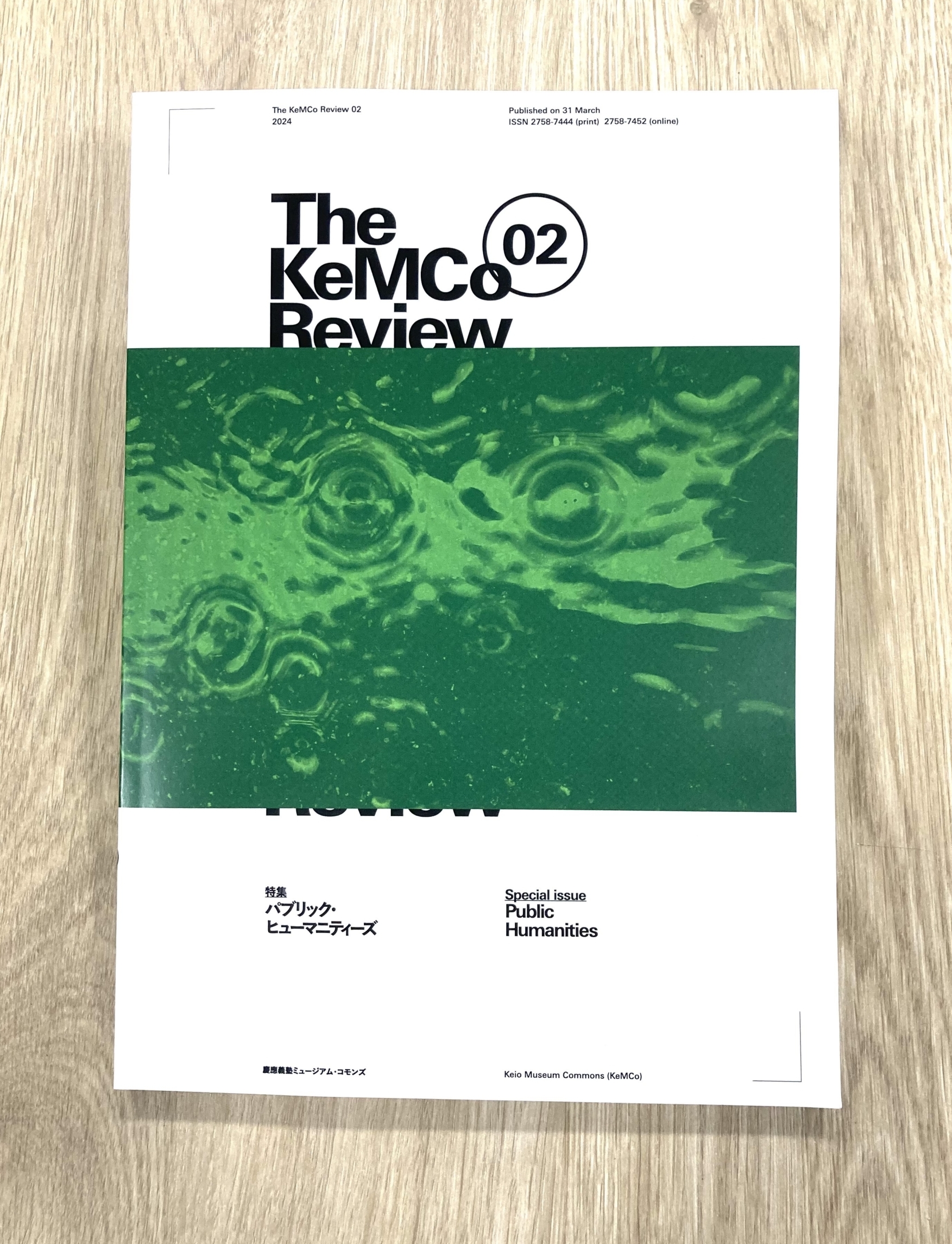The KeMCo Review 03(特集:コモニング—コモンズ的実践)
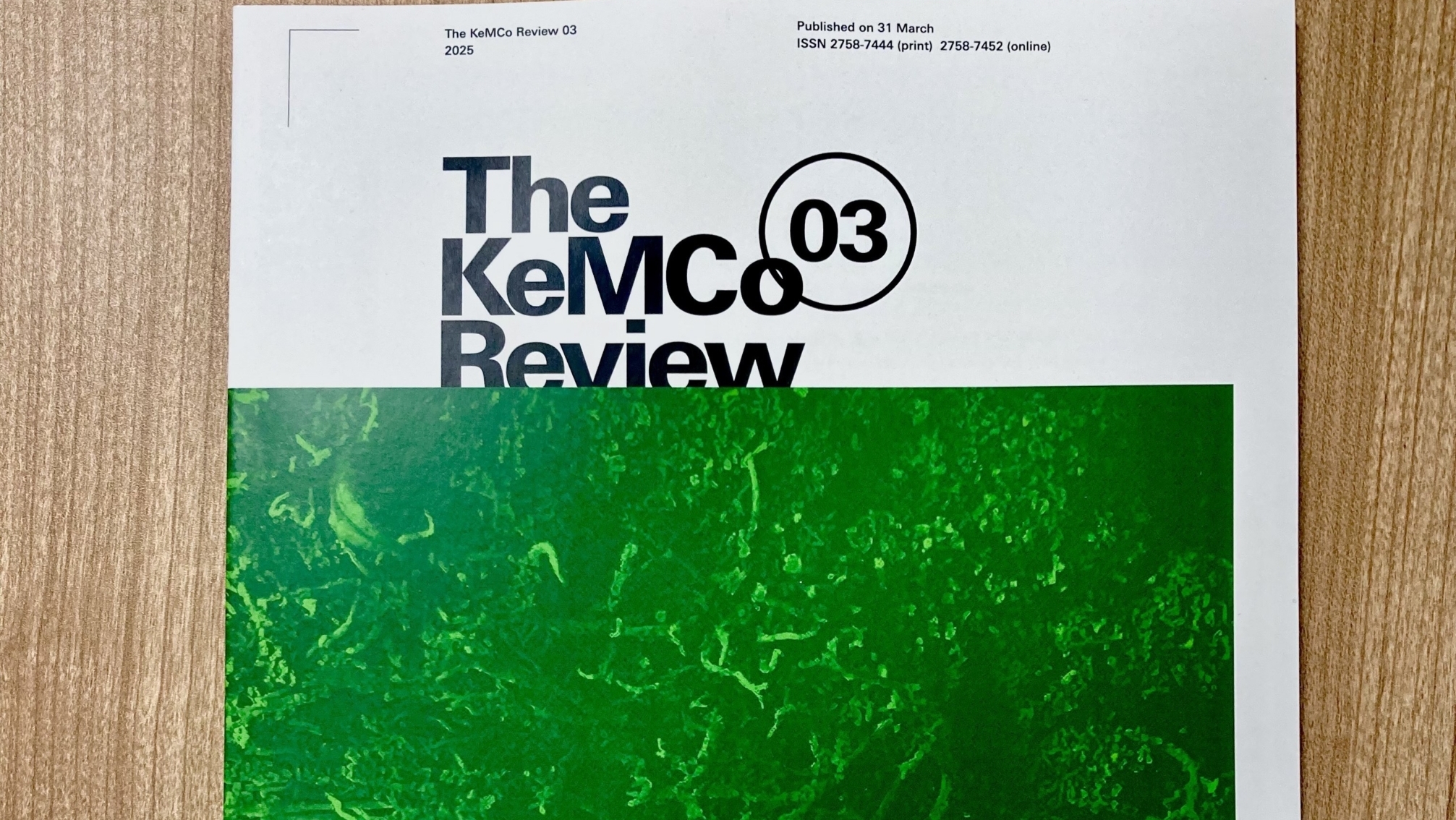
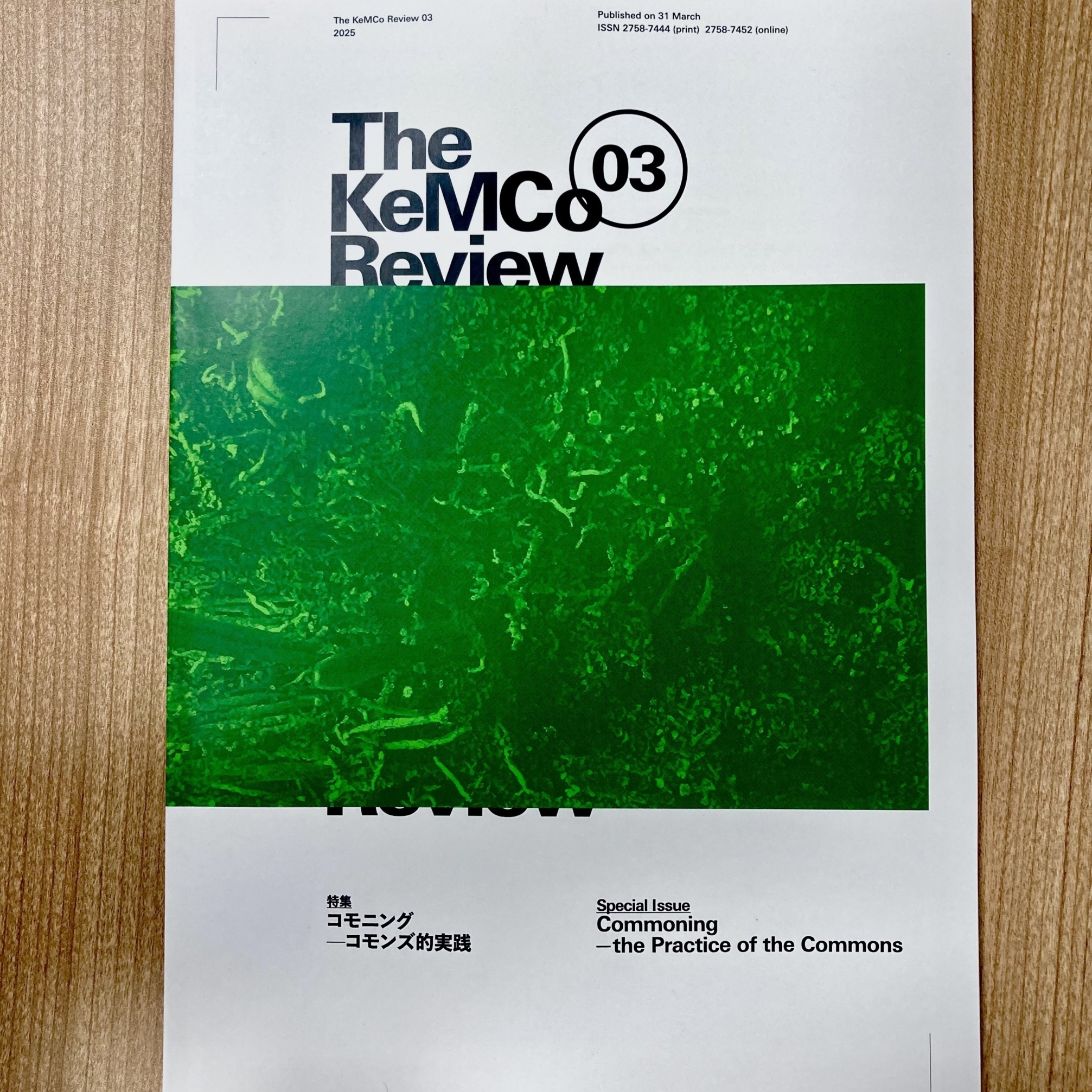
The KeMCo Review 04(特集:プリンテッド・マター Printed Matter)
お知らせページはこちら 
慶應義塾ミュージアム・コモンズ(KeMCo)では、KeMCoの活動に関連する諸領域における、学内外の研究や実践を共有化してゆくための学術誌、「The KeMCo Review 」(ケムコ レビュー)の第3号を、2025年3月に発刊しました。
目次
刊行によせて
特集 コモニング—コモンズ的実践(Commoning — the Practice of the Commons)
・マーク・トゥリン「デジタル人文学プロジェクトの帰結、あるいはデジタル・ヒマラヤの着地点」
・永崎 研宣、岡田 一祐、中川 奈津子「文化的コモンズの基盤としての情報技術をめぐるコモンズ」
・加藤 文俊「「コモニング」という場づくり:共食の実践から考える」
・佐久間 大輔「コモンズを維持成長させるミュージアムコミュニティ ―大阪市立自然史博物館の市民科学者育成
を普及誌Nature Studyから検証する―」
・本間 友、大島 志拓、重野 寛「「デジタル・コモンズ・プロジェクト」の実践:文化芸術領域におけるデジタル・コレク
ションの共同的活用と構築をめぐる考察」
・宮北 剛己、明石 枝里子「アジア太平洋地域における文化資源のデジタル化:SOI (School on Internet) Asia
の取り組み」
一般論文/研究ノート
・常深 新平「芸術作品を介したOBL(オブジェクト・ベースト・ラーニング)がもたらすもの─美術教育への活用に向け
て」
・長谷川 紫穂「メディアアートと刊行物:「Mediamatic Magazine」を事例に」
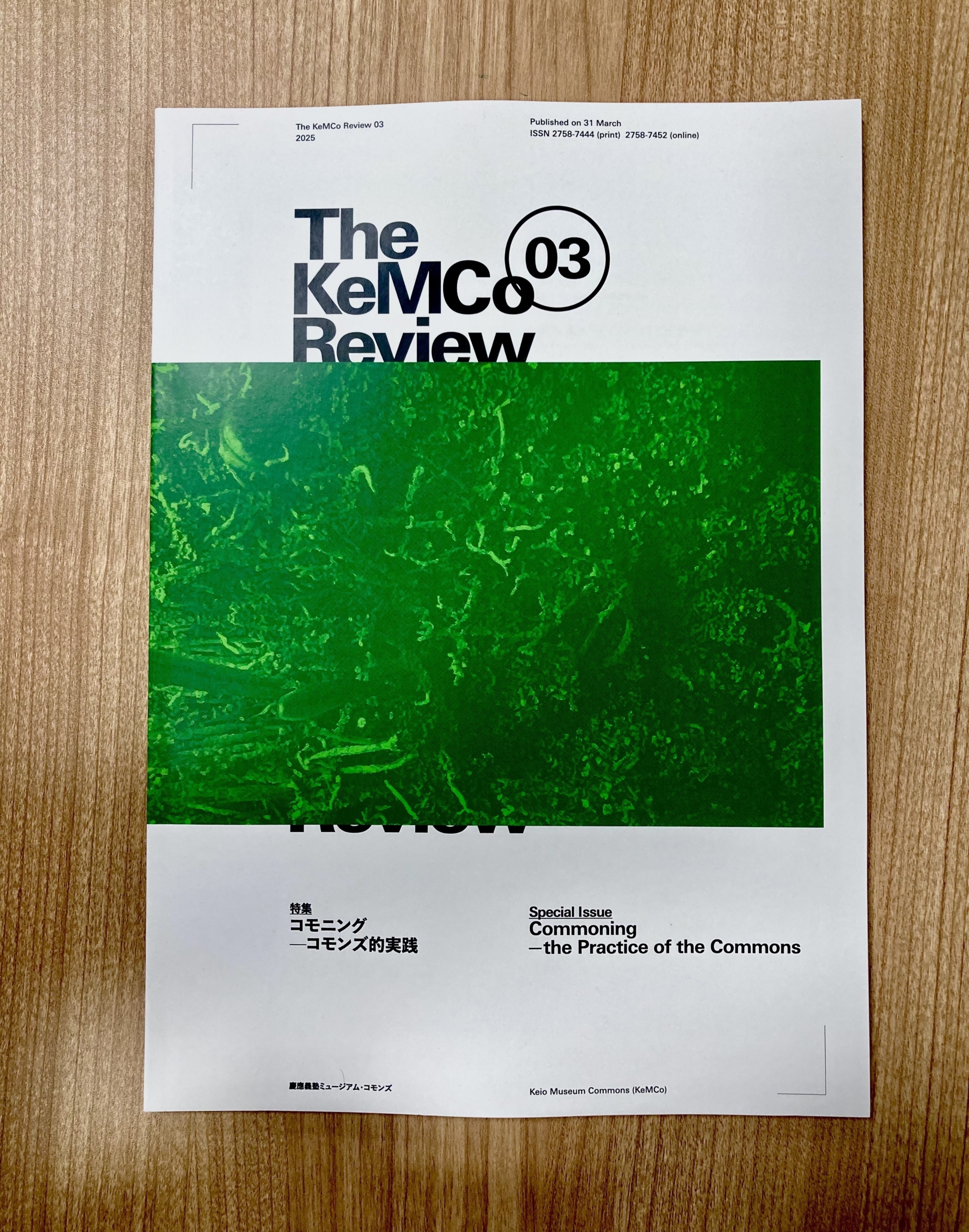
著者など
編集
慶應義塾ミュージアム・コモンズ 編集委員会
町出 美佳、長谷川 紫穂、宮北 剛己、大前 美由希、常深 新平 (慶應義塾ミュージアム・コモンズ)デザイン
尾中 俊介(Calamari Inc.)
発行
慶應義塾ミュージアム・コモンズ
判型・ページ数
B5版、120ページ
PDF
価格
無料
発行日
2025年3月31日
The KeMCo Review 03 特集 「コモニング—コモンズ的実践」
もともと「共有地」「入会地」といった空間、またそこに在する資源を指していた「コモンズ」を巡る思考は、近年大きな拡がりをみせています。共有が資源の枯渇を招くとしたハーディンの「コモンズの悲劇」(Hardin 1968)に対し、経済学・人類学・社会学などの幅広い領域の研究者が、共有地での現実の営みの分析に基いて共有制度の有用性を論じ、現代におけるコモンズ論が展開しました。
その後、コモンズ論は、オストロムによるコモンプール資源(Common Pool Resouces)の導入を契機として(Ostrom 1990)、環境資源からその射程を延ばし、情報通信、都市、知的財産権、デジタル・コンテンツ、文化など、有形無形の広範な領域に拡大しています(三俣 2010)。
文化領域のコモンズに目を移すと、日本では2010年代から議論があり(山田 2010)、これからの文化施設の果たすべき役割として「文化的コモンズ」の形成が提言されたほか(地域創造 2014, 2017)、コモンズに接続する幅広い理論や実践を渉猟した論も発表されています(佐々木 2024)。
「コモンズ」を名称とミッションに掲げる慶應義塾ミュージアム・コモンズ(KeMCo)では、文化財・文化活動に関わるコモンズとして機能すべく、多様な主体が企画に参加する展覧会、文化財を軸に対話を開く講義、収蔵庫や撮影施設の共有化など、さまざまな活動を行ってきました。2023年に公開したオンライン・コース「Akichi in Collections Management」(Keio Museum Commons 2023)では、創造的「空き地」をキーワードに共有(シェアリング)の実践と仕組み作りの重要性を取り上げました。
これまでのKeMCoの実践を振り返ると、ラインボーやハーヴェイが指摘するように(Linebaugh 2008, Harvey 2012)、コモンズは所与のものではなく、さまざまな社会的・物的環境をコモン化していく(commoning)、絶え間ない、数多の実践の中に生まれるものであることを再認識しています。
このような背景から、The KeMCo Review の第3号では、「コモニング—コモンズ的実践」を特集として設定します。大学や文化施設に留まらず、国内外の幅広いフィールドや現場において、コモンズに連なるどのような実践が行われているのか、さまざまな主体・規模・段階の実践、挑戦を、互いに共有してゆく特集としたいと考えます。みなさんの参加をお待ちしています。