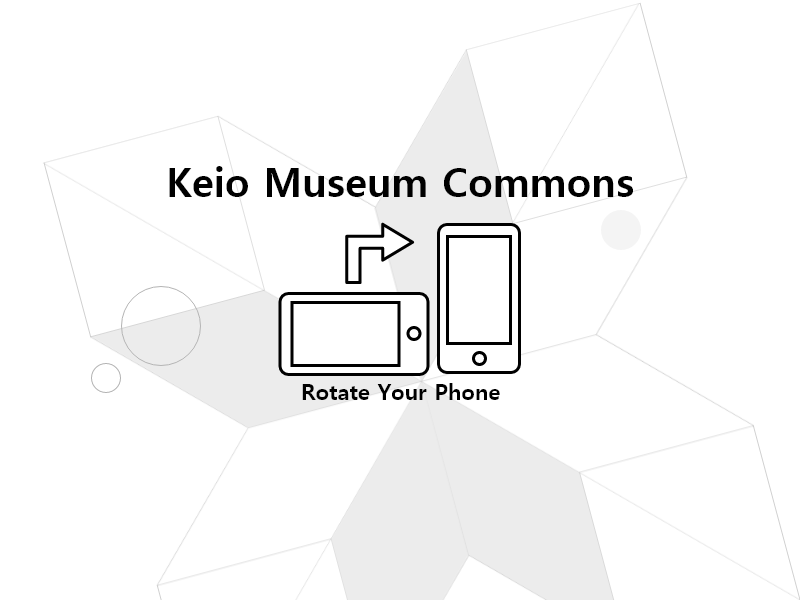The KeMCo Review 01(特集:オブジェクト・ベースト・ラーニング)
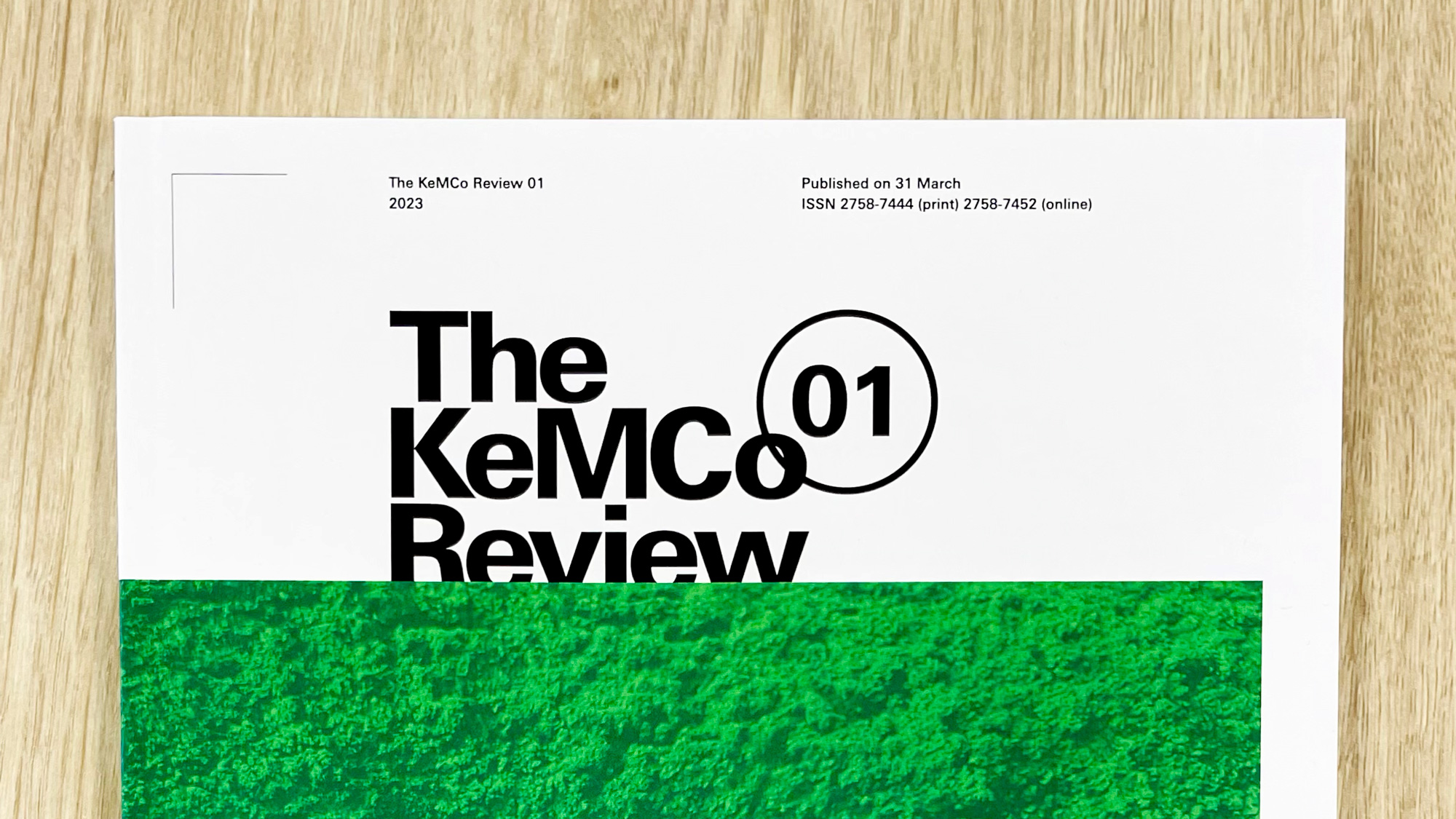
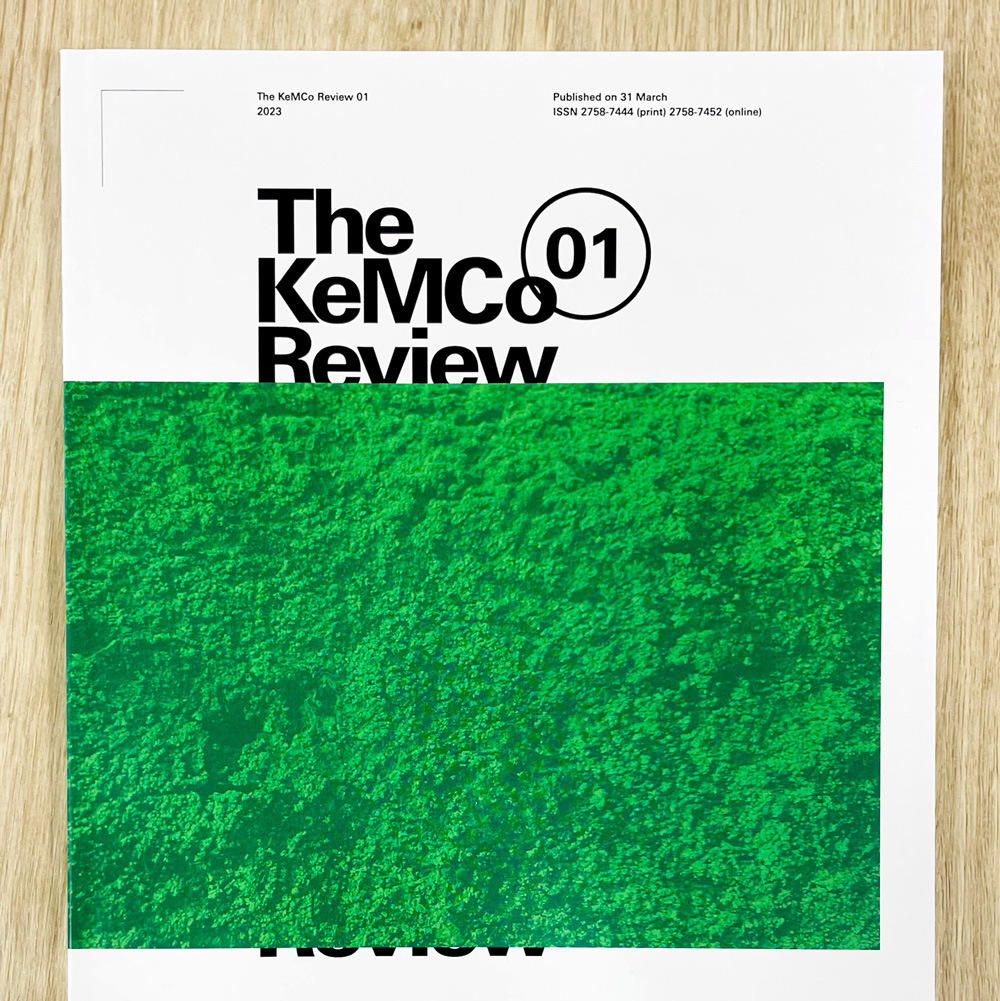
慶應義塾ミュージアム・コモンズ(KeMCo)では、KeMCoの活動に関連する諸領域における、学内外の研究や実践を共有化してゆくための学術誌、「The KeMCo Review」(ケムコ レビュー)を、2023年3月に発刊しました。
目次
刊行によせて
特集 オブジェクト・ベースト・ラーニング(Object-based Learning)
・渡部 葉子「モノを通したコミュニケーション—オブジェクト・ベースト・ラーニングの実践と可能性」
・棚橋 沙由理、白岩 志康、山本 桃子「分野横断型学習としてのオブジェクトベーストラーニングのさらなる機能拡張~人びとのウェルビーイングの向上への貢献を目指して~」
・岩間 清太朗、小久保 智淳、牛場 潤一「運動学習と『オブジェクト・ベースド・ラーニング』―神経科学の見地から―」
・本間 友「オブジェクト・ベースト・ラーニングに基づく参加型展覧会:慶應義塾ミュージアム・コモンズ『オブジェクト・リーディング:精読八景』展の再設計」
・アラヌル イミン「OBL(オブジェクト・ベースト・ラーニング)による留学生のためのKeMCo体験の創造」
・オブジェクト・ベースト・ラーニング参考文献
一般論文/研究ノート
・前川 知里「日展書部門設置による書表現の変容」
・松谷 芙美「秋田藩絵師菅原洞斎とその活動―江戸時代後期における室町水墨画の受容と研究―」
・長谷川 紫穂「情報体としての生について:アーティフィシャルライフ・アートからバイオアートへ」
・山崎 みず穂「キュレーターの役割を再考する―ニューヨーク近代美術館とソロモン・R・グッゲンハイム美術館の例から」
・荒屋鋪 透「漱石山房のヴェトゥイユ風景:夏目漱石と1915年第2回二科展「特別陳列」の安井曾太郎」
・八尾 里絵子、北市 記子、門屋 博「創造的アート・アーカイブの実践的試み- 山口勝弘の遺品整理を起点として」
・松本 守「KeMCoが生み出す教育環境:SDGsワークショップの実践を通して」
・岡原 正幸、加藤 文俊、山口 徹、小泉 明郎、本間 友、小田 浩之「アート・デザイン・コミュニケーションを身体化する場〜Keio Springコアプログラムの記録」
・宮北 剛己「オープンサイエンス時代における、人間中心アプローチを用いたデジタルアーカイブのデザイン:Keio Object Hubを事例として」
The KeMCo Review 投稿規定・執筆要領

著者など
編集
慶應義塾ミュージアム・コモンズ 編集委員会
町出 美佳、長谷川 紫穂(慶應義塾ミュージアム・コモンズ)デザイン
尾中 俊介(Calamari Inc.)
発行
慶應義塾ミュージアム・コモンズ
判型・ページ数
B5版、194ページ
PDF
価格
無料
発行日
2023年3月31日
The KeMCo Review 01 特集 「オブジェクト・ベースト・ラーニング」
オブジェクト・ベースト・ラーニングは、視覚にとどまらない、あらゆる感覚を用いてオブジェクト(モノ)と関わることによって、特定の主題に関する知識を深めるだけではなく、分野横断的な視点や、観察・実践・対話に関わる技術を獲得する学習方法と位置づけられています。
オブジェクト・ベースト・ラーニングはまた、特定の領域の教育・研究のために収集され、蓄積されてきた大学ミュージアムのコレクションに、21世紀的な教育・学習方法の文脈から新たな光を当て、その分野横断的な活用を図る試みでもあります。さらに近年では、社会・医療福祉領域、とくにウェルビーイングをめぐる実践とも接続し、ミュージアムや大学といった枠組みを越えた広がりを見せています。
KeMCoは、オブジェクト・ベースト・ラーニングについての調査、研究、実践に、開設準備室の時代から取り組んできました。2018年のOxford Dayでの講演「モノの記述を通したコミュニケーション―美術と言語の接点」(渡部葉子)を皮切りとして、慶應義塾大学アート・センターと共同した地域文化資源ワークショップでの試行を経て、2019年には、ICOM UMAC(国際博物館会議 大学博物館・コレクション国際委員会)とともに開催した国際カンファレンス「UMAC東京セミナー」において、オブジェクト・ベースト・ラーニングをテーマとする基調パネル「The Power of Objects: Practices and Prospects of Object Based Learning」を企画しました。さらに、2020年からは、設置講座「ミュージアムとコモンズ」にて、さまざまな学部・研究科にまたがる学生たちを対象に、オブジェクト・ベースト・ラーニングの方法に基づく講義を行っています。
このような背景から、The KeMCo Review の第1号では、オブジェクト・ベースト・ラーニングを特集として設定し、オブジェクト・ベースト・ラーニングに関する国内外の研究や実践を広く参照する機会とします。
大学だけではなく、ミュージアムやワークショップ等における実践や、オブジェクト・ベースト・ラーニングに接続するさまざまな取組を、人文社会科学・自然科学の分野を問わず幅広く対象とします。