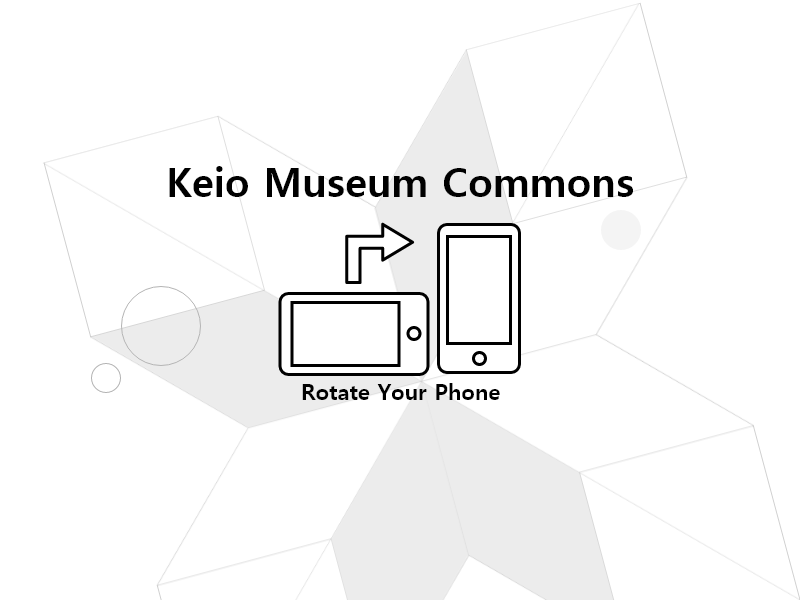
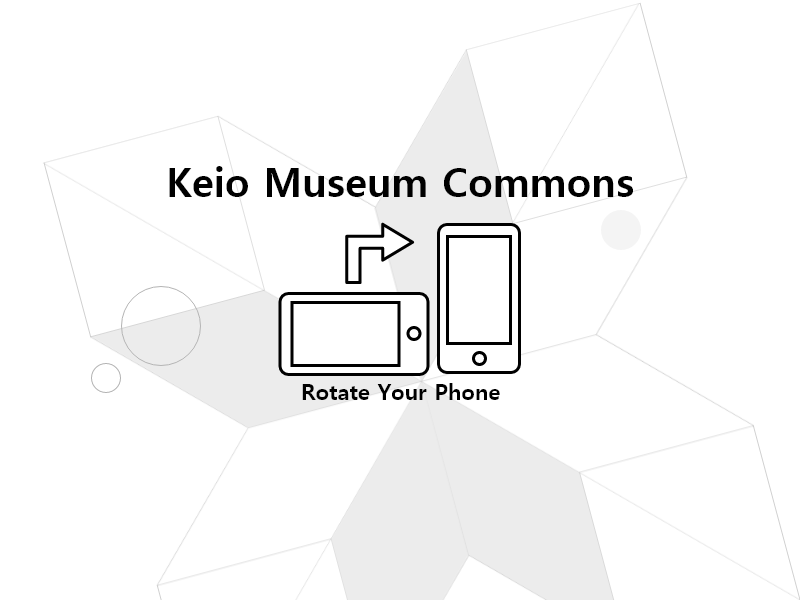

★ 2025年春学期 ガイダンスビデオ(講義の紹介)を公開しました(2025.3.9)
私たちの周囲にあるモノ(オブジェクト)は、それぞれに異なる形をもち、さまざまな意味や歴史を内包しています。そして、オブジェクトをどのように捉え、そこからなにを見いだすかは、相対するひと毎に異なり、オブジェクトはインタラクションの度に違う姿を見せます。
本講座では、アート作品や学術資料など、豊かで複雑な意味や歴史を内包するオブジェクトの観察に根ざした対話を根幹に据える「オブジェクト・ベースト・ラーニング」の方法論に基づき、自らのコンテクストを確認しながら、他者との対話を通じて対象に関する知識と理解を発展させ、多様な価値観を受け入れていく方法を学びます。
また、大学内のミュージアム、ライブラリ、アーカイヴなどの文化機関への見学を通して、様々な文化資源のもつ特徴を学び、そのデジタル化と活用に向けた展望について、デジタル・アーカイヴやデジタル・ヒューマニティーズ領域の活動を参照しながら考えます。
さらに、オブジェクトを用いた共同実習、ディスカッションを通じて、既存の前提を問い直していく思考を身につけること、また、ミュージアム・コモンズの情報環境を活用した実習を通じて、自らの思考を創造的にアウトプットする方法を学んでいくことをねらいとしています。
● 本講義は、対面での開講となります。希望者多数の場合は抽選を行う予定です。
(抽選結果は「履修申告」画面で確認できます。「不許可」の表示がない場合は、履修が許可されています。)
● 授業の概要:2025年春学期 ガイダンスビデオ(講義の紹介)を参照してください。
各学部での単位の取り扱い
2025年度は春学期と秋学期に開講します。
春と秋の講座内容は基本的に同一ですが、フィールドとして探訪する展覧会などが異なります。
| 第 1 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ① 授業の進めかた、全体テーマを確認する。OBLの基礎を学ぶ。 |
| 第 2 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ② ミュージアム・コモンズ(KeMCo)の収蔵作品を用いて、OBL実習を行う。 |
| 第 3 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ③ OBLの実習に加えて、OBLという方法論の特徴や獲得される視点についてディスカッションする。 |
| 第 4 回 | 蒐集者を引きつけるオブジェクト:古筆学者旧蔵資料展覧会 見学 人々を引きつけるオブジェクトの力、またオブジェクトを蒐集するコレクターの好奇心について、KeMCoで開催される展覧会見学に即して学ぶ。 |
| 第 5 回 | アーカイヴのオブジェクト:過去と現代を繋ぐ資料を福沢センターに訪ねる アーカイヴに収蔵されているオブジェクトの特徴や整理・研究のありかたについて、慶應義塾の歴史に関する資料を収集する慶應義塾大学福沢センターへの見学を通じて学ぶ。 |
| 第 6 回 | アートが生まれる痕跡をとどめるオブジェクト①:現代アート・アーカイヴ 見学 現代芸術を専門とする研究所、慶應義塾大学アート・センターのアーカイヴを訪問し、現代美術の制作に関わる資料の特徴や、それを整理、研究、公開するアーカイヴの活動について学ぶ。 |
| 第 7 回 | アートが生まれる痕跡をとどめる資料 ②:アーカイヴと展覧会 アート・センターが開催するアーカイヴ資料を用いた展覧会「瀧口修造と荒川修作/マドリン・ギンズ」を見学し、展覧会とアーカイヴが、資料を提示するメディアとしてどのように異なるのかを考える。 |
| 第 8 回 | メディアとアート:デジタルと表現、マテリアリティの展開 ① 現代アートにおけるデジタル・テクノロジー/メディアとの関係を概観し、メディアアートを中心としたデジタルと表現における視座を学ぶ。 |
| 第 9 回 | メディアとアート:デジタルと表現、マテリアリティの展開 ② 前週を踏まえて、アートとデジタル・テクノロジー/メディアについてのディスカッションを行う。 |
| 第 10 回 | デジタル・ワールドにおけるオブジェクトの姿 デジタル環境(ワールド)におけるオブジェクトの在り方や、デジタルデータとオブジェクトの関係性を多角的に考察する。 |
| 第 11 回 | デジタルデータとオブジェクト ① テキストやイメージをはじめとするオブジェクト(文化財)のデジタル化手法について、ケーススタディと実習を通して学ぶ。 |
| 第 12 回 | デジタルデータとオブジェクト ② デジタル・アーカイヴが文化財の保存・活用にどのような可能性をもたらすのか、ケーススタディと実習を通して学ぶ。 |
| 第13回 | デジタルデータとオブジェクト ③ デジタルとオブジェクトの新たな関係性、そして文化資源の未来像について、ディスカッションと実習を交えて学ぶ。 |
| 第14回 | ミュージアムにおけるデジタル・インタラクション デジタル技術を活用したミュージアムにおけるオブジェクトとのインタラクションを考える。 |
| 第 1 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ① 授業の進めかた、全体テーマを確認する。OBLの基礎を学ぶ。 |
| 第 2 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ② ミュージアム・コモンズ(KeMCo)の収蔵作品を用いて、OBL実習を行う。 |
| 第 3 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ③ OBLの実習に加えて、OBLという方法論の特徴や獲得される視点についてディスカッションする。 |
| 第 4 回 | 現代美術の見かたを共有する:アート・センター現代美術展覧会 見学 アート・センターで開催される現代美術展覧会(冨井大裕展)の見学を通じて、現代美術をどのように見ているのか、それぞれの視点を共有しディスカッションする。 |
| 第 5 回 | オブジェクトとしての本:慶應義塾図書館 貴重書室で西洋中世写本を見る 慶應義塾図書館(三田メディアセンター)の貴重書室を訪問し、西洋中世写本の実見を通して、本をオブジェクトとして見る視点を学ぶ。 |
| 第 6 回 | ディスカッション:さまざまなオブジェクトを見る これまでの見学を通じて、オブジェクトを見ることについてどのような気づきを得たかを共有し、ディスカッションする。 |
| 第 7 回 | 蒐集者を引きつけるオブジェクト:斯道文庫を訪ねる 人々を引きつけるオブジェクトの力について、日本及び東洋の古典に関する資料を蒐集・研究する斯道文庫への見学を通じて考える。 |
| 第 8 回 | 版本の見かたを共有する:KeMCo古活字本展覧会 見学 前週の斯道文庫への見学を踏まえ、KeMCoで開催されている江戸時代初期の古活字本の展覧会見学を通じて、版本の見かたを共有する。 |
| 第 9 回 | ディスカッション:観察して記述すること 「観察と記述」についてエスノメソドロジーの方法論を学び、状況や行為の記述についてのワークを交えながらディスカッションする。 |
| 第 10 回 | デジタルデータをオブジェクトとして見る 高度に情報化された社会のなかで、オブジェクトはどのように発展し、あるいは変容していくのか。情報化技術(デジタル)の進展を概観しつつ、その更なる可能性を展望する。 |
| 第 11 回 | デジタルデータとオブジェクト ①-1 オブジェクトをデジタルデータ化する意義や手法について学ぶ。本回では、特に三次元(3D)表現の可能性について、ケーススタディと実習を通して学ぶ。 |
| 第 12 回 | デジタルデータとオブジェクト ①-2 オブジェクトをデジタルデータ化する意義や手法について学ぶ。本回では、特に三次元(3D)表現の可能性について、ケーススタディと実習を通して学ぶ。 |
| 第13回 | デジタルデータとオブジェクト ② 人類数千年の歴史のなかで蓄積されたきたモノ・コトは、如何にして共有されえるのか。グローバルなデータ空間の仕組みと利活用について、ケーススタディと実習を通して学ぶ。 |
| 第14回 | デジタルデータとオブジェクト ③ インターネット前提時代におけるオブジェクトの未来像を展望しつつ、デジタルデータとオブジェクトの関係性が生み出す新たな価値について、ディスカッションと実習を交えて学ぶ。 |
※ 本設置講座は、慶應義塾大学の正規在籍者のみを対象としています。学外の方の履修・聴講はできません。